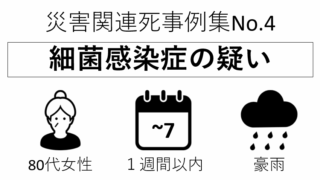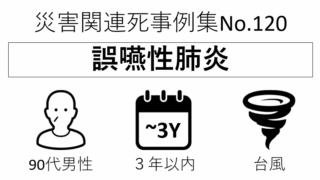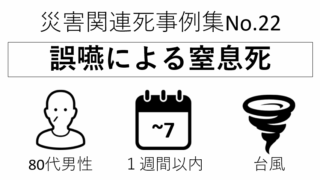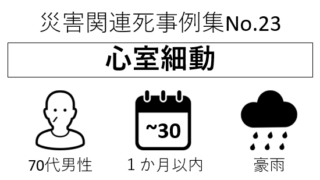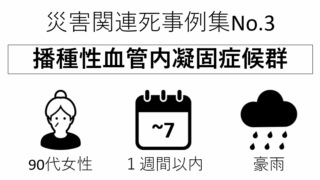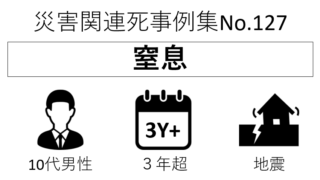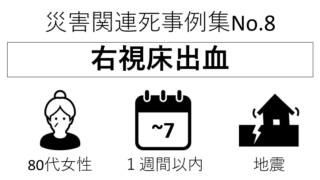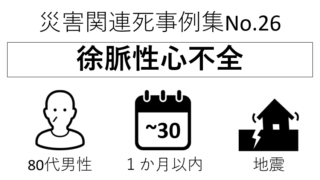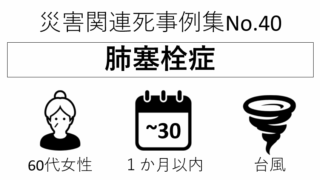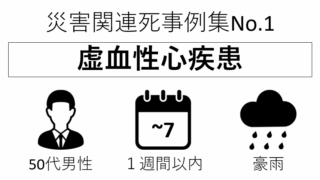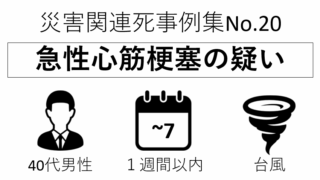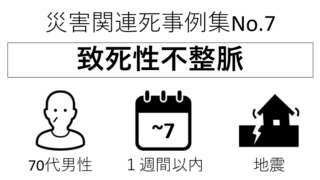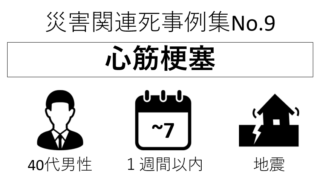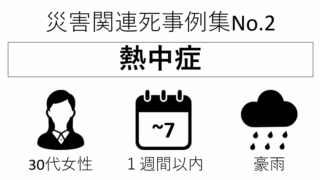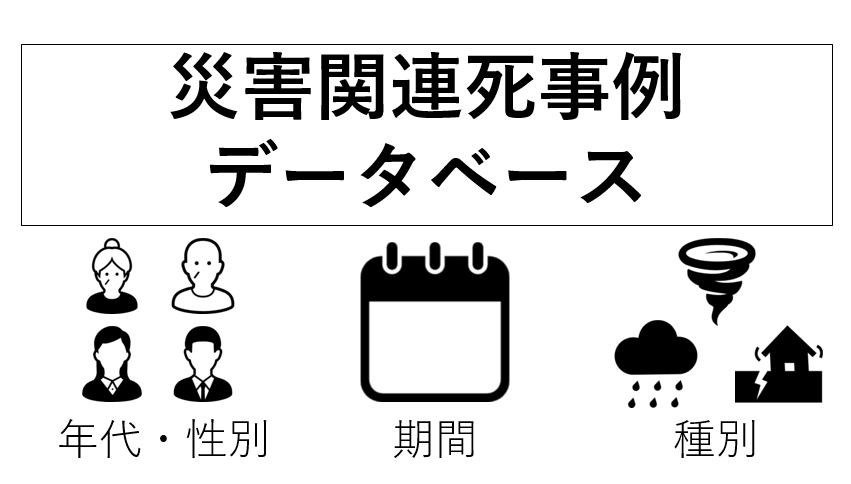災害関連死の考え方等
災害関連死の定義
当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和 48 年法律第 82 号)に基づき災害が原因で死亡したものと認められたもの(実際には災害弔慰金が支給されていないものも含めるが、当該災害が原因で所在が不明なものは除く。)
地震による建物の倒壊や津波などによる直接的・物理的な原因ではなく、災害による負傷の悪化や避難生活等の身体的負担による疾病により死亡する、いわゆる「災害関連死」については、平成7年に発生した阪神・淡路大震災、平成 23 年に発生した東日本大震災、平成 28 年に発生した熊本地震など、大規模な災害が発生した際、報道等において取り上げられたが、政府における明確な定義はなかった。
政府においては、従来から、災害時において避難生活等が原因で亡くなる、いわゆる災害関連死を少しでも減らすよう、政府全体として避難所の生活環境の改善に取り組んできたところであるが、災害関連死を減らすためには、まずはその数を把握することが重要であるという認識の下で、平成 31 年4月に次のように災害関連死の定義を定め、関係省庁と共有するとともに自治体への周知を行った。
なお、定義では、「当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡」とあるところ、避難生活等における身体的負担によるものであれば、精神疾患による自殺も含まれることとしている。
災害関連死の定義の解説
① 定義では、「災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき災害が原因で死亡したものと認められたもの」とあるが、どのように判断するのか。
⇒災害による死亡であるかどうかは、いわゆる相当の因果関係により判断するものである。
なお、災害による死亡は即時のみに限定されるものでなく、負傷しその負傷が原因で療養中に死亡した場合も含まれる。
② 定義では、「当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡」とあるが、避難生活等における身体的負担による疾病を苦に精神的に追い込まれて自殺した場合は、含まれないのか。
⇒避難生活等における身体的負担によるものであれば、精神疾患による自殺も含まれるものである。
③ 「実際には災害弔慰金が支給されていないものも含める」場合の事例としてはどのようなものがあるのか。
⇒1 夫婦関係が実際には破たんしているなど受給対象でないことが認定後に分かって災害弔慰金が支払われなかったケース。
※市町村への申請時には遺族がおり、災害による死亡と認められたものの、弔慰金を支払うまでに遺族がいなくなってしまった場合もあり得る。
⇒2 直接死ではなく、災害に関連して消防団員等が亡くなり、その遺族が、(賞じゅつ金をもらうことも視野に入れて)市町村に申請して認定されたケース。
※賞じゅつ金が支払われた場合には、災害弔慰金は支払われないことになっている。
④ 定義では、「当該災害が原因で所在が不明なものは除く。」としているのはどうしてか。
⇒当該災害が原因で3カ月間所在が不明なものについては、当該災害によって死亡したものと推定されるため、定義に記載している「災害が原因で死亡したと認められるもの」に該当するが、従来から死者ではなく行方不明者としてカウントしているため、災害関連死から除くこととした。
⑤ 弔慰金の支給の対象となる遺族以外の方が、災害関連死の判定をして欲しいという依頼があった場合には、支給の対象とならない中でも、審査会等を開き、災害関連死の判断をしなければならないか。
⇒弔慰金の支給の対象となる遺族以外の方が、災害関連死の判定をして欲しい旨、依頼があった場合には、審査会等を開いて災害関連死の判断をするかどうかは、従来どおり自治体の判断である。
⑥ 当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担により死亡した、同居や生計を同一にしていない兄弟姉妹等についても、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づくものではなく自治体が独自にいわゆる弔慰金を支給した場合は、災害関連死になるのか。
⇒災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき災害が原因で死亡したものと認められるものではないため、災害関連死ではない。
⑦ 被災地で活動するボランティアが、熱中症などで亡くなった場合に、災害関連死になる可能性はあるのか。
⇒災害関連死の認定は、死亡の原因が災害に関連するものであるかどうかについて、市町村がいわゆる相当の因果関係により判断するため、災害の種類や被災者の状況等によって異なるものと考えている。
災害による疲労で熱中症になり、心筋梗塞で亡くなった住民を災害関連死と認めた例は承知しているが、被災地で活動するボランティアが熱中症などで亡くなった場合に災害関連死と認めた例は承知していないところ。